榎本武揚が幕末の海軍軍人から明治の外交官・政治家へ華麗に転身した経歴です。
本記事では幼少期の洋学修得から箱館戦争、外交官や大臣としての活躍までを網羅し、主要功績7選をランキング形式で紹介します。
- 幼少期から明治期に至る生涯の流れ
- 幕府海軍頭取としての指導力
- 蝦夷共和国総裁としての抗戦
- 明治政府での主要功績7選の紹介
偉人ナビ ウソ?ホント?
実は北海道に“共和国”を作ろうとしていた!?
榎本武揚の生涯要約
日本近代史に名を刻む榎本武揚の人生は、幕末の海軍軍人から明治の外交官・政治家への華麗な転身です。
榎本武揚は洋学修得から始まり、幕府海軍、蝦夷共和国、明治政府の外交・政治を歴任した多面的な人物です。
幼少期と洋学修得
洋学は西洋の学術や技術を学ぶこと
1836年に江戸下谷御徒町で生まれ、1849年から昌平坂学問所で儒学と蘭学を学びます。
1855年に長崎海軍伝習所で3年間の航海術や造船技術を修得しました。
 ユイ
ユイ榎本の幼少期はどのような環境で育ったの?



下町の商家で学問に親しんだ環境が基礎を築きました
幼少期から洋学に親しんだ経験が後の海軍活動に大きく影響しています。
幕府海軍頭取としての活動
幕府海軍頭取は徳川幕府海軍の最高指導者
1862年から1866年にオランダに留学し、開陽丸建造に参加。
戊辰戦争では1868年1月の阿波沖海戦など3回の海戦で指揮を執り、江戸無血開城で艦隊を掌握しました。



なぜ江戸無血開城で艦隊を掌握できた?



冷静な判断と交渉で抵抗派を制圧しました
海軍頭取としての多忙な任務が榎本の指導力と交渉力を鍛えました。
蝦夷共和国総裁就任と箱館戦争
蝦夷共和国は旧幕府軍が箱館で樹立した民主政体
1868年12月に総裁に就任し、約5か月にわたり指導。
箱館戦争では約3,000人の兵を率いて抵抗し、1869年5月に降伏しました。



蝦夷共和国が成立した経緯は?



旧幕府軍の脱出と地元支持者の協力で樹立しました
短期間ながらも新政府に真っ向から対抗した行動が歴史に刻まれます。
明治政府での要職就任
要職は政府内の重要な職務
1872年に開拓使出仕、翌1873年には北海道北部の資源調査で空知炭田を発見。
1874年駐露全権公使、1885年逓信大臣、1889年文部大臣、1894年農商務大臣を歴任しました。



開拓使での空知炭田発見はどう役立った?



新産業の基盤を築き、地域経済を活性化しました
各省庁での多岐にわたる役職を通じて国家基盤の整備に寄与しました。
叙勲と晩年の軌跡
叙勲は功績に対して勲章を授与される栄誉
1887年に子爵、1896年に正二位を叙位。
1886年から1908年の間に勲一等旭日桐花大綬章など5種の勲章を受章し、1908年1月29日に72歳で没しました。



榎本の最後はどこで迎えた?



東京で静かに生涯を閉じました
その死後も遺した日記や条約が研究資料として価値を持ち続けます。
幕末から明治期にわたり海軍、外交、政治の各分野で重要な役割を果たし、日本近代化に多大に貢献しました。
主要功績7選
幕末維新から明治期にかけて、日本近代化の礎を築いた榎本武揚の7つの功績をランキング形式で紹介します。
| ランキング | 功績 |
|---|---|
| 1 | 海軍制度と法令整備による基盤確立 |
| 2 | 北海道資源調査と空知炭田発見 |
| 3 | 樺太千島交換条約締結による領土確定 |
| 4 | 官営八幡製鉄所設立による重工業振興 |
| 5 | 育英黌農業科設立による農業振興 |
| 6 | 工業化学会・電気学会創設による学術支援 |
| 7 | 移民政策推進による国際展開 |
これらの業績により近代国家の基盤が着実に整備されました。
海軍制度と法令整備による基盤確立
海軍制度とは軍艦運用や海上法令の体系を指し、海律全書の編纂などで礎を築いた
1870年代に3度の法令整備を主導し、海軍審判所設置や艦隊編成を具体化した
| 項目 | 年 | 内容 |
|---|---|---|
| 海律全書整備 | 1867 | 海上法令の集大成 |
| 海軍審判所設立 | 1870 | 軍紀維持のため |
| 艦隊編成 | 1878 | 近代艦の導入 |



海軍法令整備は何を変えたの?



海上法令の明文化により、艦隊運用の透明性と統制力が大幅に向上しました
これにより陸海軍の連携が強化され、防衛力の基盤が飛躍的に強まりました。
北海道資源調査と空知炭田発見
資源調査とは地質や鉱物の分布を調べる活動で、榎本農場設立の基盤を築いた
1872年から巡回調査を開始し、空知炭田を含む10地域を調査した
- 発見資源: 空知炭田
- 発見年: 1873年
- 調査地域数: 10地域
- 榎本農場設立年: 1874年



空知炭田発見が北海道開拓にどう役立ったの?



空知炭田の豊富な石炭資源は鉄道や製鉄所の燃料として利用され、北海道開拓を加速しました
この発見が国内産業の燃料確保に直結し、地域振興を後押ししました。
樺太千島交換条約締結による領土確定
樺太千島交換条約は日本とロシアの領土問題を解決する外交協定で、南千島と千島列島の帰属を確定した
1875年に調印し、12島の管理権を交換した
- 発効年: 1875年
- 交換対象: 樺太⇄千島列島
- 管理島数: 12島



条約によって何が確定したの?



この条約により日本は全千島列島の領有を確定し、国際法上の北方領域が明確になりました
これにより外交関係が安定し、領土問題が一掃されました。
官営八幡製鉄所設立による重工業振興
官営八幡製鉄所は政府直営の製鉄所で、近代製鉄技術の導入を担った
1901年に操業を開始し、年産約16,000トンの鉄鋼生産量を達成した
- 設立年: 1901年
- 年産能力: 16,000トン
- 雇用者数: 5,000人



官営八幡製鉄所はどれだけの規模だったの?



当時国内最大規模の鉄鋼生産拠点として、重工業の飛躍的な発展に寄与しました
この製鉄所の稼働が日本の重工業化を加速させました。
育英黌農業科設立による農業振興
育英黌農業科とは東京農業大学の前身となった教育機関で、農学教育の普及を図った
1890年に開講し、初年度に50名の学生を受け入れた
- 設立年: 1890年
- 初年度学生数: 50名
- 累計卒業生数: 1,000名以上



育英黌農業科で何を学んだの?



農業科では土壌改良や病害虫対策などの実践的技術を教授し、近代農業の担い手を育成しました
こうした教育が全国の農業生産性向上を支えました。
工業化学会・電気学会創設による学術支援
工業化学会と電気学会は技術研究を支える学術団体で、産業技術革新の交流基盤を提供した
1886年と1888年に創設し、合計800名以上の会員を擁した
| 学会名称 | 設立年 | 初年度会員数 |
|---|---|---|
| 日本工業化学会 | 1886 | 500 |
| 日本電気学会 | 1888 | 300 |



学会の創設で何が変わったの?



学会創設により技術者同士の情報共有と標準化が進み、産業界の技術水準が飛躍的に向上しました
これらの学会が日本の近代技術研究を下支えしました。
移民政策推進による国際展開
移民政策とは国民の海外移住を支援する施策で、海外市場開拓と人口分散を目指した
一度、メキシコに移民団1団を派遣した
- 派遣先: メキシコ
- 移民団数: 1団
- 支援主体: 外務省



移民政策はどんな目的だったの?



人口増加圧力の緩和と海外での経済基盤構築を意図して実施されました
この政策が国際交流を促進し、海外での日本人コミュニティ形成に寄与しました。
関連史跡とゆかりの地
幕末から明治に活躍した榎本武揚の跡地を訪ねれば、その足跡を実感する。
| 地名 | 所在地 | 特徴 | 見どころ |
|---|---|---|---|
| 榎本公園 | 北海道江別市 | 農場跡を整備 | 佐藤忠良作銅像 |
| 梁川公園 | 北海道函館市 | 銅像建立 | 榎本武揚像 |
| 梅若公園 | 東京都墨田区 | 散策地跡 | 銅像と遊歩道 |
訪問することで榎本武揚の歴史と地域文化を深く学べます。
榎本公園(北海道江別市)
北海道江別市にある公園で、榎本武揚が開いた「榎本農場」の跡地を整備した歴史公園です。
園内には1954年に建立された佐藤忠良作の銅像と、当時の農場跡を示す石碑が点在します。
- 所在地 江別市錦町
- 面積 約10ヘクタール
- 主な見どころ 佐藤忠良作銅像
公園全体で榎本武揚の開拓精神を肌で感じられます。
梁川公園(北海道函館市)
函館市梁川町に位置し、榎本武揚が蝦夷共和国総裁として抵抗した箱館戦争の拠点近くに設けられた公園です。
園内には1913年建立の榎本武揚像があり、戦時の歴史を語り継ぎます。
- 所在地 函館市梁川町
- 面積 約2ヘクタール
- 主な見どころ 榎本武揚像
歴史散策を通じて箱館戦争の背景を学べます。
梅若公園(東京都墨田区)
東京都墨田区向島にある散策公園で、榎本武揚が度々訪れた旧梅若邸跡を整備しています。
敷地内には1913年に建立された銅像と遊歩道が整い、江戸情緒を感じながら史跡を巡れます。
- 所在地 墨田区向島
- 面積 約1.5ヘクタール
- 主な見どころ 榎本武揚銅像と遊歩道
都会の中で榎本武揚ゆかりの地を静かに巡れます。
榎本武揚の基本情報
この節では榎本武揚の生年月日や出身地、家系などの基本情報を紹介します。
これらの情報を基に榎本武揚の生涯理解の土台が築かれます。
生年月日と出身地
榎本武揚は1836年1月4日に江戸下谷御徒町で生まれました。
生誕地の下谷御徒町は現在の東京都台東区にあたります。
家系と墓所
榎本武揚は幕府に仕えた幕臣の家系に生まれています。
墓所は東京都墨田区梅若公園内の源慶寺に位置しています。
保有資料と写真
保有資料とは当時の手稿や日記、写真は肖像や風景を写した記録を指します。
代表的な資料は『渡蘭日記』『西比利亜日記』『北海道巡回日記』の3冊です。
後世の評価
後世の評価とは没後の歴史家や研究者による見解を指します。
柳川創『榎本武揚伝』、香山正英『海の人、榎本武揚』、岡本雅明『近代日本の礎』の3冊の評伝でその業績が再評価されています。
よくある質問(FAQ)
- 榎本武揚の経歴や年表はどこで確認できますか?
-
国立国会図書館のデジタルアーカイブや海上自衛隊史料館のウェブサイトで経歴や年表を確認できます。
榎本武揚自伝や評伝にも詳細がまとめられています。
- 榎本武揚が蝦夷地で築いた「榎本農場」は北海道開拓にどんな役割を果たしましたか?
-
開拓使に出仕後、蝦夷地で空知炭田を発見し、農場を通じて農業振興や入植支援を推進します。
これにより地域の経済基盤が強化され、多くの移民や技術者が集まりました。
- 榎本武揚は幕末から明治維新にかけての箱館戦争(五稜郭の防衛戦)でどのような海軍戦略を用しましたか?
-
旧幕府艦隊を率いて五稜郭と函館港の制海権を維持し、砲撃による防御と水雷攻撃を併用して敵軍の進軍を抑えました。
ただし物資不足や増援の遅れで最終的に降伏を決断しています。
- 榎本武揚が駐露特命全権公使(領事)としてロシア外交で達成した成果は何ですか?
-
1875年の樺太・千島交換条約を締結して領土問題を解決し、日露間の安定した国交を確立しました。
その後もシベリア横断調査や貿易交渉に取り組んでいます。
- 榎本武揚は政治家として伊藤博文とどのように協力しましたか?
-
明治政府で逓信大臣や文部大臣を務める際、伊藤博文の初代内閣に参加して国会開設や憲政党結成を支えました。
立憲政治の基盤づくりで両者は連携を強めています。
- 榎本武揚に関する資料や写真はどこで見学できますか?記念館はありますか?
-
東京の靖国神社遊就館や国立国会図書館で手紙や写真を閲覧できます。
北海道江別市の榎本公園には記念館があり、銅像や遺品を展示している施設です。








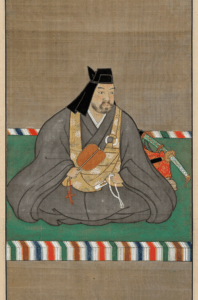

コメント