篠原泰之進の生涯を理解するうえで最も重要なのは、幕末から明治に至る10の節目によって示される多彩な歩みです。
この記事は生年月日や出身地といった基本情報から武術修行、主要業績、政府要職就任までをわかりやすくまとめています。
 ユイ
ユイレポート用に篠原泰之進のプロフィールと業績を手早く把握したい



生年月日から著作、政府要職まで10の節目で全体像をつかめます
- 生年月日と幼名
- 出身地と家系
- 武術修行の流派
- 10の主要業績
偉人ナビ ウソ?ホント?
西南戦争で“最後まで抜刀突撃”を命じた気骨の士だった!?
篠原泰之進のプロフィール概要
プロフィールを把握するうえで最も重要なのは基本情報の正確性です。
以下で生年月日と幼名、出身地と家系、学歴と武術修行、主要な経歴の流れを順に確認します。
結論として、彼の出自と修行が後の活動を支えました。
生年月日と幼名
幼名とは、幼少期に使用される本名とは別の名前です。
1828年12月22日生まれで、幼名は泰輔です。
こうした生年月日と幼名が彼の人生の出発点となります。
出身地と家系
家系とは、祖先から続く血筋を指す言葉です。
筑後国生葉郡高見村(現福岡県うきは市浮羽町)出身で、父・元助は旧姓秦を名乗りました。
丸橋忠弥の血筋を引くという説も伝わっています。
こうした出身地と家系が彼の価値観に影響を与えました。
学歴と武術修行
武術修行は武芸を体得するための稽古期間を意味します。
1852年から江戸で修行を開始し、槍術・剣術の久留米藩森兵右衛門流と種田宝蔵院流、柔術の良移心当流と揚心古流、それに北辰一刀流剣術を含む5流派を修めました。
こうした多様な流派での鍛錬が彼の技術を高めました。
主要な経歴の流れ
篠原泰之進の経歴は約60年にわたる活動で構成されます。
1852年に江戸へ赴いた後、1861年の水戸滞在、1865年の新選組加盟、1868年の戊辰戦争参加、明治2年の弾正台少巡察就任、明治5年の大蔵省造幣使監察役就任、晩年の回顧録執筆といった主要な節目を刻みました。
| 年 | 内容 |
|---|---|
| 1852年 | 小倉一之進に仕え江戸へ赴任 |
| 1861年 | 水戸滞在で尊王攘夷思想に触れる |
| 1863年 | 神奈川奉行所で横浜居留地警備 |
| 1865年 | 新選組加盟・柔術師範兼監察 |
| 1867年 | 御陵衛士参加・油小路事件後離脱 |
| 1868年 | 赤報隊参戦 |
| 1869年 | 弾正台少巡察就任 |
| 1872年 | 大蔵省造幣使監察役就任 |
| 晩年 | キリスト教入信および『秦林親日記』執筆 |
こうした流れから彼の多彩な役割が浮かび上がります。
篠原泰之進の主要業績10選
幕末から明治期にかけての10の節目が篠原泰之進の多彩な歩みを象徴しています。
| 順位 | 業績 |
|---|---|
| 1 | 文政11年生誕と幼名改名 |
| 2 | 水戸滞在と尊王攘夷運動参加 |
| 3 | 神奈川奉行所での警備任務 |
| 4 | 新選組加盟と柔術師範就任 |
| 5 | 御陵衛士結成と油小路事件離脱 |
| 6 | 赤報隊参加と投獄経験 |
| 7 | 会津戦争北越戦争での戦功 |
| 8 | 明治政府要職就任(弾正台少巡察) |
| 9 | 大蔵省造幣使監察役 |
| 10 | 秦林親日記執筆とキリスト教入信 |
これらの節目が彼の生涯を具体的に形づくっています。
1 文政11年生誕と幼名改名
文政11年は江戸時代後期の年号で、篠原泰之進は1828年12月22日に生まれています。
筑後国生葉郡高見村(現福岡県うきは市浮羽町)で幼名泰輔として誕生しました。



幼名ってどんな意味があるの?



幼名は子供時代に用いる名前です
幼名泰輔を賜ったことで家系と地域への所属意識が強まりました。
2 水戸滞在と尊王攘夷運動参加
尊王攘夷運動は幕府打倒を唱える政治運動で、1861年に篠原は33歳で水戸に滞在しました。
江戸大攘夷論に触れて政治的志向を深めています。



水戸での活動は具体的に何を行ったの?



尊王攘夷の志を抱いて論議に参加しました
水戸滞在の経験がその後の行動に大きな影響を与えました。
3 神奈川奉行所での警備任務
神奈川奉行所は幕府直轄の行政機関で、1863年に篠原は外国人居留地の警備を担当しました。
横浜の治安維持と外交交渉に従事しています。



なぜ警備任務に就いたのですか?



幕府から要請を受けて勤めました
警備任務で組織運営と対外対応の実務能力を磨きました。
4 新選組加盟と柔術師範就任
新選組は京都守護職直属の治安部隊で、1865年に篠原は柔術師範兼監察として入隊しました。
隊士の訓練と規律維持を担っています。



なぜ新選組に加わったの?



幕府防衛に貢献するためです
柔術師範として隊士の戦闘力向上に寄与しました。
5 御陵衛士結成と油小路事件離脱
御陵衛士は天皇陵を警護する部隊で、1867年に結成に参加しました。
油小路事件後に新選組を離脱し独自活動へ移行しています。



油小路事件とは何ですか?



1867年に新選組と薩摩藩が衝突した事件です
離脱後は自身の志に即した道を歩みました。
6 赤報隊参加と投獄経験
赤報隊は農民救済を掲げた志士集団で、1868年に参加後すぐに投獄されました。
釈放後は再び会津戦争に復帰しています。
投獄の挫折を乗り越えて戦場に戻りました。
7 会津戦争北越戦争での戦功
会津戦争と北越戦争は戊辰戦争の主要戦線で、篠原は両戦役で複数の戦闘を指揮しました。
戦功により恩賞金250両と終身扶持8人を得ています。



どんな戦功を挙げたの?



先遣隊の指導などで戦果を上げました
戦績が明治新政府での待遇を左右しました。
8 明治政府要職就任(弾正台少巡察)
弾正台少巡察は士族統制を担当する官職で、明治2年に就任しました。
旧幕臣の取り扱いと司法監督を行っています。



弾正台少巡察の役割は?



士族の動向を監視し秩序を維持する職です
行政経験の土台となる重要な役割でした。
9 大蔵省造幣使監察役
造幣使監察役は大蔵省内で造幣所の監督を担う職で、明治5年に任命されました。
新しい通貨制度の整備に携わっています。



造幣使監察役の仕事内容は?



造幣所の運営管理と品質検査を行います
通貨制度確立への貢献が後世に残る役割となりました。
10 秦林親日記執筆とキリスト教入信
『秦林親日記』は篠原自身の回顧録で、晩年に編纂しました。
明治末期にキリスト教に入信し、洗礼を受けました。



日記と入信はどのように残っていますか?



回顧録と洗礼証書が現在も国立公文書館で閲覧可能です
晩年の著作と信仰が人物像に深い洞察を与えています。
篠原泰之進の学歴と武術流派
武術の学びは彼の行動原理を支えた基盤であり、多様な流派の修得経験が最も重要です。
| 流派名 | 種別 | 特徴 |
|---|---|---|
| 久留米藩森兵右衛門流槍術剣術 | 槍術・剣術 | 久留米藩伝統の実戦型 |
| 種田宝蔵院流剣術 | 剣術 | 標的割打ちに優れる |
| 揚心古流柔術 | 柔術 | 関節技と投げ技重視 |
| 北辰一刀流剣術 | 剣術 | 江戸の高弟から学ぶ |
これらを並行して学んだことで、篠原泰之進は武術技術の多角的な見識を確立しました。
久留米藩森兵右衛門流槍術剣術
久留米藩森兵右衛門流槍術剣術は、江戸時代に久留米藩で伝承された実戦向きの槍術と剣術を組み合わせた流派です。
稽古では長槍の構えや短刀を用いた二刀流の基本動作を徹底して身につけています。
その結果、戦場での対応力を高めています。
種田宝蔵院流剣術修行
種田宝蔵院流剣術は対人斬撃技を重視した江戸後期の剣法です。
刺突と斬り込みの連続動作を厳格に鍛錬し、形式片手返しや二刀併用の技術を習得しました。
結果として、実戦での制圧力を強化しています。
揚心古流柔術習得
揚心古流柔術は相手の重心を崩して制する投げ技と関節技を組み合わせる和式格闘術です。
摑み技や投げ技の連続応用を重ね、寝技での絞め技も習得しました。
その結果、近距離での突発的な襲撃に対応できる柔軟性を獲得しました。
北辰一刀流剣術取り組み
北辰一刀流剣術は江戸北辰派に伝わる剣術流派で、一刀の打突を極めることで知られます。
彼は江戸の高弟に師事し、真剣による試合稽古で間合いの感覚を磨きました。
結果として、敵の動きを瞬時に察知する技量を身につけています。
篠原泰之進関連の参考資料と一次情報
一次資料の信頼性が研究の精度を左右するため、正確な所蔵先を把握することが重要です。
| 資料名 | 主な所蔵内容 | 利用方法 |
|---|---|---|
| 国立公文書館デジタルアーカイブ | 幕末維新期の公文書デジタル化 | オンライン検索 |
| 福岡県うきは市郷土資料館 | 出生地関連の戸籍・家系図 | 来館閲覧(予約制) |
| 青山霊園管理事務所の墓所情報 | 墓所区画位置・建立記録 | 来園問い合わせ |
| 秦林親日記回顧録 | 本人回顧録原本(写本) | 国立公文書館で申請閲覧 |
上記の一次資料を参照して論述の裏付けとしてください。
国立公文書館デジタルアーカイブ
デジタルアーカイブは、政府機関や文化財を電子化して公開するシステムです。
数十点の篠原泰之進関連文書がオンラインで閲覧可能です。
- 明治2年弾正台少巡察報告書
- 慶応元年新選組加入記録
- 秦林親日記の写本



オンラインで文書を利用する手順は?



検索画面で「篠原泰之進」と入力して絞り込むと見つかります
オンライン検索機能を活用すると目的の文書に迅速にアクセスできます。
福岡県うきは市郷土資料館
郷土資料館は地域の歴史資料を収集・保管・公開する施設です。
数百点の戸籍や系譜資料を所蔵しています。
- 出生地高見村の戸籍原本
- 幼名「泰輔」に関する系図
- 浮羽町当時の地図写真



現地で閲覧する方法は?



事前予約のうえ、郷土資料館の閲覧室で閲覧可能です
利用時間内に予約番号を提示すると閲覧室で資料を確認できます。
青山霊園管理事務所の墓所情報
墓所情報は墓地の区画位置や建立年月を示すデータです。
84歳没時の墓所区画が記録されています。
- 墓所位置:4区3番3側
- 墓碑銘:秦林親
- 移転履歴:なし



墓所までのアクセス方法は?



東京メトロ銀座線外苑前駅から徒歩10分で管理事務所に到着します
外苑前駅から徒歩で訪れると短時間で管理事務所に到達できます。
秦林親日記回顧録
回顧録は本人が経験を時系列に振り返って記した記録です。
全6冊、約300ページに及ぶ写本が確認できます。
- 巻数:6冊
- 執筆期間:1868年~1910年
- 主な内容:戊辰戦争や明治期の活動回想



日記の閲覧方法は?



国立公文書館で閲覧申請すると原本または複写版を利用できます
申請手続きを行うとオリジナルと複写版のいずれかを閲覧できます。
よくある質問(FAQ)
- 篠原泰之進の生年月日と出身地は何ですか?
-
篠原泰之進は文政11年11月16日(西暦1828年12月22日)に生まれ、筑後国生葉郡高見村(現福岡県うきは市浮羽町)出身です。
- 篠原泰之進の学歴と武術修行はどのようなものですか?
-
藩校などでの学問記録は限られていますが、久留米藩の森兵右衛門流で槍術と剣術、種田宝蔵院流の剣術、良移心当流と揚心古流の柔術、さらに北辰一刀流の剣術を学びました。
- 篠原泰之進の経歴にはどのような実績がありますか?
-
尊王攘夷運動への参加、水戸や横浜での警備、新選組加盟と柔術師範就任、御陵衛士結成、赤報隊参加、鳥羽・伏見の戦いや会津・北越戦争での戦功、明治政府の弾正台少巡察や大蔵省造幣使監察役就任など多彩な経歴を築きました。
- 篠原泰之進の仕事と事業内容について教えてください。
-
維新後は終身扶持や恩賞金を得て弾正台少巡察、大蔵省造幣使監察役など公的な仕事を務めました。
実業活動には成功せず、事業内容として特定の会社経営は行っていません。
- 篠原泰之進の著書や参考文献は何がありますか?
-
自身の回顧録として『秦林親日記』を残しています。
一次資料は国立公文書館デジタルアーカイブや福岡県うきは市郷土資料館、青山霊園管理事務所で確認できます。
- 篠原泰之進の最新情報やメディア掲載を確認するにはどこが良いですか?
-
歴史研究誌の最新号やウェブ版で連載される人物紹介、国立公文書館のデジタルアーカイブ更新、地域の郷土資料館サイトで新発見情報や展示会案内をチェックすると最新情報が得られます。





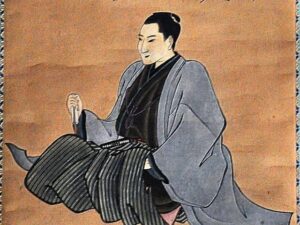

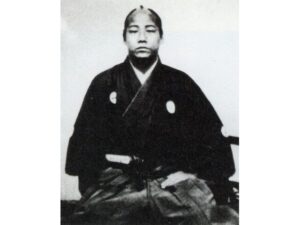
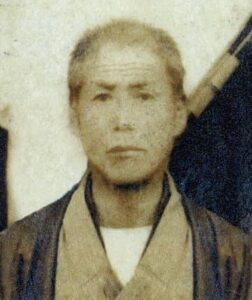
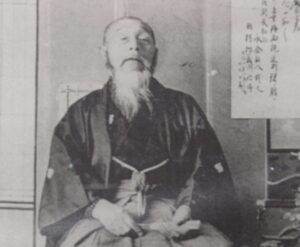
コメント